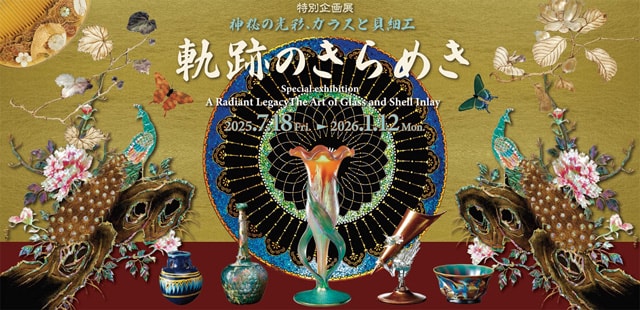
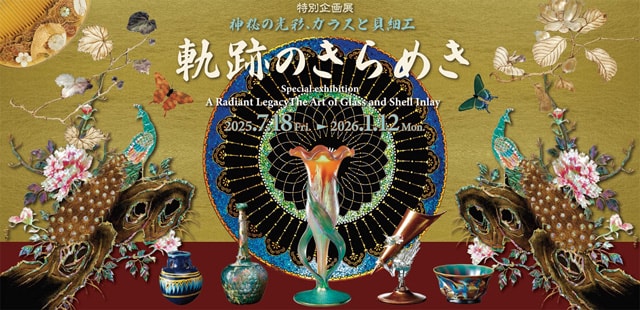
展示ケースに掲示されている番号に合わせてご視聴ください。
美術館内ではイヤホン等を使用するか、ボリュームを下げてご利用ください。
FREE Wi-Fiをご利用ください。 SSID:Venetian_Glass_Museum
はじめに

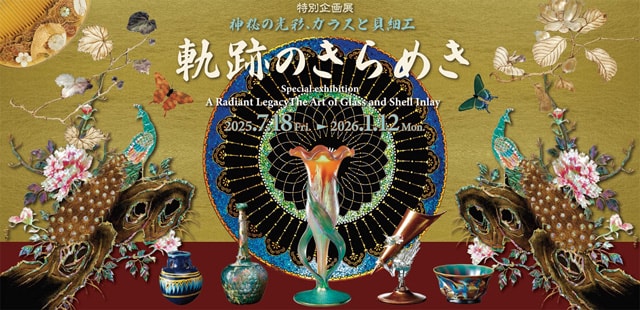
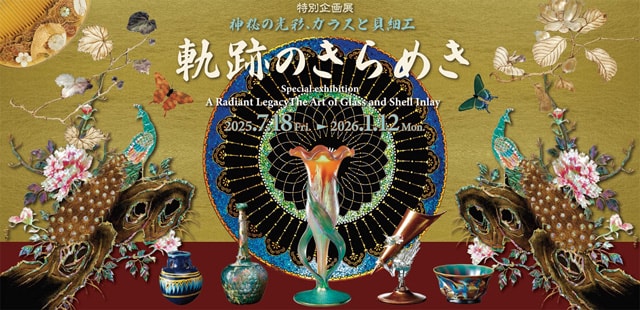
展示ケースに掲示されている番号に合わせてご視聴ください。
美術館内ではイヤホン等を使用するか、ボリュームを下げてご利用ください。
FREE Wi-Fiをご利用ください。 SSID:Venetian_Glass_Museum
はじめに

1.長頸香油瓶

(1~3世紀│東地中海沿岸域)
約4000年前に生まれ、貴重品だったガラス。当初は耐火粘土に熔けたガラスを巻き付けて成形した小さな瓶が主流でした。ガラス工芸に革命が訪れたのは約2000年前、古代ローマ帝国で「吹きガラス」技法が発明された事によります。吹き竿の先に熔けたガラスを巻き付け、息を吹き込んで成形するこの技法により、ガラスの大量生産が可能となり、多くの人々に届くようになりました。
この細長い首のガラス瓶は、香油を入れる容器として使われました。香油は植物などから抽出した香りを油に移したもので、地中海世界の人々が好んで使用していました。
ガラス表面にご注目ください。この幻想的な輝きは「銀化」と呼ばれ、長年地中に埋もれていたガラスが風化し、層状に変化したガラス表面に光が反射することで生まれる虹色のきらめきです。
様々な角度から、移ろう神秘的な美しさをご覧ください。
1.長頸香油瓶

(1~3世紀│東地中海沿岸域)
約4000年前に生まれ、貴重品だったガラス。当初は耐火粘土に熔けたガラスを巻き付けて成形した小さな瓶が主流でした。ガラス工芸に革命が訪れたのは約2000年前、古代ローマ帝国で「吹きガラス」技法が発明された事によります。吹き竿の先に熔けたガラスを巻き付け、息を吹き込んで成形するこの技法により、ガラスの大量生産が可能となり、多くの人々に届くようになりました。
この細長い首のガラス瓶は、香油を入れる容器として使われました。香油は植物などから抽出した香りを油に移したもので、地中海世界の人々が好んで使用していました。
ガラス表面にご注目ください。この幻想的な輝きは「銀化」と呼ばれ、長年地中に埋もれていたガラスが風化し、層状に変化したガラス表面に光が反射することで生まれる虹色のきらめきです。
様々な角度から、移ろう神秘的な美しさをご覧ください。
2.二重円圏カット装飾香油瓶

(9~10世紀│イラン~中央アジア)
二重の円文様のカット装飾が彫り込まれた香油瓶。サーサーン朝ペルシアで流行した大ぶりの切子碗などに用いられたカット装飾は、後のイスラーム時代、香油瓶などの装飾に受け継がれました。
こちらの香油瓶の幻想的な輝きは「銀化」と呼ばれ、古代ガラスにみられる珍しい現象です。長い間地中に埋もれていたガラスは、地下水などの影響を受け、表面のアルカリ成分が徐々に溶け出し、雲母のように薄い膜が重なった状態になります。その表面に光が反射することで、虹色のきらめきが生まれます。
この発色は「構造色」と呼ばれ、見る角度や光のあたり具合によって色が変わる、不思議な現象です。ガラスと自然が織りなす神秘的なきらめきをご堪能ください。
2.二重円圏カット装飾香油瓶

(9~10世紀│イラン~中央アジア)
二重の円文様のカット装飾が彫り込まれた香油瓶。サーサーン朝ペルシアで流行した大ぶりの切子碗などに用いられたカット装飾は、後のイスラーム時代、香油瓶などの装飾に受け継がれました。
こちらの香油瓶の幻想的な輝きは「銀化」と呼ばれ、古代ガラスにみられる珍しい現象です。長い間地中に埋もれていたガラスは、地下水などの影響を受け、表面のアルカリ成分が徐々に溶け出し、雲母のように薄い膜が重なった状態になります。その表面に光が反射することで、虹色のきらめきが生まれます。
この発色は「構造色」と呼ばれ、見る角度や光のあたり具合によって色が変わる、不思議な現象です。ガラスと自然が織りなす神秘的なきらめきをご堪能ください。
3.マーブル装飾扁壺

(12~13世紀│シリアあるいはエジプト)
白い羽根のようなマーブル模様が印象的なガラス壷。琥珀色のガラス素地の所々に銀化が見られ、青緑色の光沢を放っています。細長い首と先細りの形状は、イスラーム時代に普及したバラ水瓶によく見られる特徴です。
この作品は吹きガラス技法で作られていますが、装飾は紀元前1世紀頃まで東地中海沿岸で盛んだったコア・グラスによく使われた技法で表現されています。この模様は、熔けた色ガラスを器に巻き付け、固まる前に上下に引っかく事で生み出され、コア・グラスから吹きガラスに移行した後も受け継がれました。
3.マーブル装飾扁壺

(12~13世紀│シリアあるいはエジプト)
白い羽根のようなマーブル模様が印象的なガラス壷。琥珀色のガラス素地の所々に銀化が見られ、青緑色の光沢を放っています。細長い首と先細りの形状は、イスラーム時代に普及したバラ水瓶によく見られる特徴です。
この作品は吹きガラス技法で作られていますが、装飾は紀元前1世紀頃まで東地中海沿岸で盛んだったコア・グラスによく使われた技法で表現されています。この模様は、熔けた色ガラスを器に巻き付け、固まる前に上下に引っかく事で生み出され、コア・グラスから吹きガラスに移行した後も受け継がれました。
4.螺鈿細工蒔絵洋櫃

(桃山時代│日本)
16世紀後半、ポルトガル人が種子島に到来したことから始まる「南蛮貿易」。桃山時代、ポルトガルやスペインとの交易で日本から最も多く輸出されたのが、この蒲鉾形の蓋の付いた海賊の宝箱のような形状の洋櫃でした。
洋櫃は、日本の職人がヨーロッパの人々の要望を反映して制作した輸出品でした。現在も修道院などで、輸出された当時の品が大切に残されています。
こちらの洋櫃には、金や銀の粉を用いた蒔絵や、貝殻の光沢を生かした螺鈿が贅沢に施され、鳥や鹿、桔梗を思わせる植物が華やかに装飾されています。
4.螺鈿細工蒔絵洋櫃

(桃山時代│日本)
16世紀後半、ポルトガル人が種子島に到来したことから始まる「南蛮貿易」。桃山時代、ポルトガルやスペインとの交易で日本から最も多く輸出されたのが、この蒲鉾形の蓋の付いた海賊の宝箱のような形状の洋櫃でした。
洋櫃は、日本の職人がヨーロッパの人々の要望を反映して制作した輸出品でした。現在も修道院などで、輸出された当時の品が大切に残されています。
こちらの洋櫃には、金や銀の粉を用いた蒔絵や、貝殻の光沢を生かした螺鈿が贅沢に施され、鳥や鹿、桔梗を思わせる植物が華やかに装飾されています。
5.貝細工酒器

(江戸時代│日本)
貝細工による一式の酒器。天然の貝殻の形状を生かし、脚や注ぎ口は別の貝で作られ、丁寧に成形されています。
かのペリー提督が下田港から同様の品を黒船に積み込んだとされる記録が残っています。江戸時代から明治、大正時代にかけて、こうした貝細工の酒器が人々の間で親しまれました。
材料のヤコウガイは、螺鈿細工にも使用される真珠のような光沢を持ち、貝殻の内側の炭酸カルシウムの層に光が干渉する事で、神秘的な虹色のきらめきが生まれます。この作品は螺鈿細工とは異なりますが、貝本来の形や質感、艶やかな光沢を生かし、粋な江戸の人々の遊び心があふれる作品となっています。
5.貝細工酒器

(江戸時代│日本)
貝細工による一式の酒器。天然の貝殻の形状を生かし、脚や注ぎ口は別の貝で作られ、丁寧に成形されています。
かのペリー提督が下田港から同様の品を黒船に積み込んだとされる記録が残っています。江戸時代から明治、大正時代にかけて、こうした貝細工の酒器が人々の間で親しまれました。
材料のヤコウガイは、螺鈿細工にも使用される真珠のような光沢を持ち、貝殻の内側の炭酸カルシウムの層に光が干渉する事で、神秘的な虹色のきらめきが生まれます。この作品は螺鈿細工とは異なりますが、貝本来の形や質感、艶やかな光沢を生かし、粋な江戸の人々の遊び心があふれる作品となっています。
6.青貝細工手元箪笥

(明治時代|日本)
一面に螺鈿が輝く手元箪笥。箪笥の前面、側面、背面へと続く水流に沿って、80名を超える人々や水鳥が生き生きと表現されています。螺鈿に使用される貝殻は、青みを引き出すため0.1ミリ程の厚さまで薄く研ぎ出され、一部の貝は裏面から着色することで、幅広い色彩を表現しています。職人の技術力の高さが感じられる作品です。
螺鈿の意匠は、中国・東晋の時代、王羲之が蘭亭で開いた「曲水の宴」の場面を表現し、清流に流れる盃が通り過ぎる前に詩を作り、間に合わなければ酒を飲み干すという優雅な遊びが行われました。平安時代の日本の宮廷でも、この宴を模して詩と酒が楽しまれました。
繊細に表現された中国の故事の場面と、きらめく色彩をご覧ください。
6.青貝細工手元箪笥

(明治時代|日本)
一面に螺鈿が輝く手元箪笥。箪笥の前面、側面、背面へと続く水流に沿って、80名を超える人々や水鳥が生き生きと表現されています。螺鈿に使用される貝殻は、青みを引き出すため0.1ミリ程の厚さまで薄く研ぎ出され、一部の貝は裏面から着色することで、幅広い色彩を表現しています。職人の技術力の高さが感じられる作品です。
螺鈿の意匠は、中国・東晋の時代、王羲之が蘭亭で開いた「曲水の宴」の場面を表現し、清流に流れる盃が通り過ぎる前に詩を作り、間に合わなければ酒を飲み干すという優雅な遊びが行われました。平安時代の日本の宮廷でも、この宴を模して詩と酒が楽しまれました。
繊細に表現された中国の故事の場面と、きらめく色彩をご覧ください。
7.青貝細工入り寄木細工

(明治時代|日本)
寄木細工と螺鈿が輝く箪笥。寄木細工は現在箱根が有名ですが、こちらの作品は静岡で作られました。かつて徳川家光が浅間神社改修のため、各地から名工を集めた事により、漆や螺鈿を組み合わせた寄木細工が発展しました。
寄木細工は、さまざまな色の木片を組み合わせて幾何学模様を作り、表面に貼り付ける技法です。静岡の寄木細工は「乱寄木」と呼ばれる不規則な模様が特徴で、漆を塗って仕上げられます。
両開き扉の雉と牡丹の装飾には、貝の裏側から赤や青などの着色を施す「青貝細工」が用いられています。これは「伏彩色」とも呼ばれ、螺鈿の色彩をより鮮やかに表現できる技法です。
寄木だけではなく、漆や螺鈿の技術を組み合わせた、静岡ならではの贅沢な箪笥の細部にご注目ください。
7.青貝細工入り寄木細工

(明治時代|日本)
寄木細工と螺鈿が輝く箪笥。寄木細工は現在箱根が有名ですが、こちらの作品は静岡で作られました。かつて徳川家光が浅間神社改修のため、各地から名工を集めた事により、漆や螺鈿を組み合わせた寄木細工が発展しました。
寄木細工は、さまざまな色の木片を組み合わせて幾何学模様を作り、表面に貼り付ける技法です。静岡の寄木細工は「乱寄木」と呼ばれる不規則な模様が特徴で、漆を塗って仕上げられます。
両開き扉の雉と牡丹の装飾には、貝の裏側から赤や青などの着色を施す「青貝細工」が用いられています。これは「伏彩色」とも呼ばれ、螺鈿の色彩をより鮮やかに表現できる技法です。
寄木だけではなく、漆や螺鈿の技術を組み合わせた、静岡ならではの贅沢な箪笥の細部にご注目ください。
8.横浜芝山細工花蝶図飾盆

(明治時代|日本)
草花や蝶を牛骨や白蝶貝から精巧に彫り出し、色漆に立体的に象嵌した飾り盆です。飾り盆の周囲に施された木目は、筆による彩色で表現されています。
芝山漆器は、江戸時代後期、上総国、現在の千葉県、芝山の大野木専蔵が考案した、立体的な象嵌を用いた作品です。大野木専蔵が江戸でこの技法を完成させると、その精緻な作品は諸大名の間で評判となりました。
横浜が開港したのち、華やかな浮き彫りが嵌め込まれた芝山漆器は人気を博し、訪日外国人や海外需要の急増に応じて発展。需要の高まりにより、芝山漆器の職人たちが横浜に移り住み、制作を続けたことで横浜芝山漆器として広く知られるようになりました。この飾り盆も、イギリスから日本に里帰りした横浜芝山漆器の優れた一例です。
漆と貝殻のグラデーションが織りなす、花と蝶の繊細な造形をご堪能ください。
8.横浜芝山細工花蝶図飾盆

(明治時代|日本)
草花や蝶を牛骨や白蝶貝から精巧に彫り出し、色漆に立体的に象嵌した飾り盆です。飾り盆の周囲に施された木目は、筆による彩色で表現されています。
芝山漆器は、江戸時代後期、上総国、現在の千葉県、芝山の大野木専蔵が考案した、立体的な象嵌を用いた作品です。大野木専蔵が江戸でこの技法を完成させると、その精緻な作品は諸大名の間で評判となりました。
横浜が開港したのち、華やかな浮き彫りが嵌め込まれた芝山漆器は人気を博し、訪日外国人や海外需要の急増に応じて発展。需要の高まりにより、芝山漆器の職人たちが横浜に移り住み、制作を続けたことで横浜芝山漆器として広く知られるようになりました。この飾り盆も、イギリスから日本に里帰りした横浜芝山漆器の優れた一例です。
漆と貝殻のグラデーションが織りなす、花と蝶の繊細な造形をご堪能ください。
9.イボカブリモドキ (Coptolabrus Pustulifer)

(2017年│橋本千毅│日本)
麻布に漆を塗り重ねる乾漆技法で成形したプレートに、漆を削り出して造形した昆虫を配したペンダント。モチーフは「歩く宝石」と称されるオサムシの一種。モデルとなった当の昆虫は、体表の薄い膜に光が反射することで、虹色の輝きを放ちます。
漆芸家の橋本千毅は、鮑などの貝殻から削り出した真珠層を色調ごとに細かく分類し、表現したい色彩を作り上げます。螺鈿のきらめきを調整しながら微細なパーツをモザイク状に貼り合わせる技法で制作され、一つの作品が完成するまでに膨大な時間を必要とします。
作家の思いとこだわりに満ちた作品が放つ、神秘的なきらめきをご覧ください。
9.イボカブリモドキ (Coptolabrus Pustulifer)

(2017年│橋本千毅│日本)
麻布に漆を塗り重ねる乾漆技法で成形したプレートに、漆を削り出して造形した昆虫を配したペンダント。モチーフは「歩く宝石」と称されるオサムシの一種。モデルとなった当の昆虫は、体表の薄い膜に光が反射することで、虹色の輝きを放ちます。
漆芸家の橋本千毅は、鮑などの貝殻から削り出した真珠層を色調ごとに細かく分類し、表現したい色彩を作り上げます。螺鈿のきらめきを調整しながら微細なパーツをモザイク状に貼り合わせる技法で制作され、一つの作品が完成するまでに膨大な時間を必要とします。
作家の思いとこだわりに満ちた作品が放つ、神秘的なきらめきをご覧ください。
10.船形水差

(16世紀中頃|ヴェネチア)
水の都ヴェネチアを象徴する船形の水差し。富を運ぶ船のモチーフは16世紀以降、人々の間で広く愛されました。かつては頂点にイルカ、器に持ち手が取り付けられていたと考えられ、青いガラスのアクセントが無色透明ガラスの透明感を美しく際立たせています。
当時、貴族の間では水晶の彫り物が人気を博し、その希少性から水晶は富の象徴とされていました。ヴェネチアのガラス職人は、水晶のような透明ガラスを生み出すため、ガラスの発色に関する実験を重ねました。ガラス原料に由来する着色を打ち消す金属酸化物を加えたり、原料を精製して発色に影響する不純物を取り除いたりする試行錯誤の末、水晶のように透明なガラスを生み出すことに成功しました。
10.船形水差

(16世紀中頃|ヴェネチア)
水の都ヴェネチアを象徴する船形の水差し。富を運ぶ船のモチーフは16世紀以降、人々の間で広く愛されました。かつては頂点にイルカ、器に持ち手が取り付けられていたと考えられ、青いガラスのアクセントが無色透明ガラスの透明感を美しく際立たせています。
当時、貴族の間では水晶の彫り物が人気を博し、その希少性から水晶は富の象徴とされていました。ヴェネチアのガラス職人は、水晶のような透明ガラスを生み出すため、ガラスの発色に関する実験を重ねました。ガラス原料に由来する着色を打ち消す金属酸化物を加えたり、原料を精製して発色に影響する不純物を取り除いたりする試行錯誤の末、水晶のように透明なガラスを生み出すことに成功しました。
11.花装飾脚オパールセント・グラス・ゴブレット

(1880年頃│ヴェネチア│サルヴィアーティ工房)
乳白色ガラスの花装飾が美しい、脚部と坏身からなる大型の装飾坏。19世紀末に制作された観賞用の器で、高さは40センチにおよびます。
見る角度でオパールのように色彩が変化する「オパールセント・グラス」は、17世紀末から18世紀初頭に発明されました。その透明感のある優しいグラデーションが人々を魅了し、19世紀末のヴェネチアで再び人気を博します。
宝石のオパールは二酸化ケイ素の層に光が反射して色を変えますが、このオパールセント・グラスは、ガラス中のリン酸化合物への光の干渉により、色彩が移り変わります。
繊細な装飾と調和した、柔らかなガラスの色彩をご堪能ください。
11.花装飾脚オパールセント・グラス・ゴブレット

(1880年頃│ヴェネチア│サルヴィアーティ工房)
乳白色ガラスの花装飾が美しい、脚部と坏身からなる大型の装飾坏。19世紀末に制作された観賞用の器で、高さは40センチにおよびます。
見る角度でオパールのように色彩が変化する「オパールセント・グラス」は、17世紀末から18世紀初頭に発明されました。その透明感のある優しいグラデーションが人々を魅了し、19世紀末のヴェネチアで再び人気を博します。
宝石のオパールは二酸化ケイ素の層に光が反射して色を変えますが、このオパールセント・グラスは、ガラス中のリン酸化合物への光の干渉により、色彩が移り変わります。
繊細な装飾と調和した、柔らかなガラスの色彩をご堪能ください。
12.ドルフィン形脚赤色コンポート

(19世紀|ヴェネチア)
水の都ヴェネチアを象徴する愛らしいドルフィンが装飾されたコンポート。器に型押しされた菱形文様が光を反射し、美しい赤色が目を引きます。
ガラスで赤を発色するにはセレニウムなどの金属を使用しますが、この作品に見られるルビーレッドと呼ばれるピンクがかった赤色は、金を微粒子状にガラスに分散させる高度な技術で発色させています。発色剤として金を用いる技法は、17世紀初頭の書物でも紹介されていますが、古代ローマ時代には既に金による赤色ガラスが存在し、発色に挑戦した職人たちの長い試行錯誤の歴史がうかがえます。
熟練したガラス職人の経験と技によって生み出された、鮮やかなルビーレッドの輝きをご覧ください。
12.ドルフィン形脚赤色コンポート

(19世紀|ヴェネチア)
水の都ヴェネチアを象徴する愛らしいドルフィンが装飾されたコンポート。器に型押しされた菱形文様が光を反射し、美しい赤色が目を引きます。
ガラスで赤を発色するにはセレニウムなどの金属を使用しますが、この作品に見られるルビーレッドと呼ばれるピンクがかった赤色は、金を微粒子状にガラスに分散させる高度な技術で発色させています。発色剤として金を用いる技法は、17世紀初頭の書物でも紹介されていますが、古代ローマ時代には既に金による赤色ガラスが存在し、発色に挑戦した職人たちの長い試行錯誤の歴史がうかがえます。
熟練したガラス職人の経験と技によって生み出された、鮮やかなルビーレッドの輝きをご覧ください。
13.アヴェンチュリン・マーブル・グラス碗

(17世紀|ヴェネチア)
15世紀後半、ヴェネチアのガラス職人は、銀の酸化物など複数の金属酸化物を混ぜ合わせることで、メノウや大理石のような天然石の模様を作り出すことに成功しました。
このマーブル・グラスは、光の方向で色彩が移り変わり、光を透過すると夕日のような赤色に変化します。この特徴から「カルチェドーニオ」と呼ばれ、王侯貴族の間で高く評価されました。
表面にきらめく斑点は、17世紀にヴェネチアで発明された「アヴェンチュリン・グラス」によるもの。銅の結晶を含んだガラスが、自然界の鉱物の中で輝く砂金のようなきらめきを、効果的に表現しています。
13.アヴェンチュリン・マーブル・グラス碗

(17世紀|ヴェネチア)
15世紀後半、ヴェネチアのガラス職人は、銀の酸化物など複数の金属酸化物を混ぜ合わせることで、メノウや大理石のような天然石の模様を作り出すことに成功しました。
このマーブル・グラスは、光の方向で色彩が移り変わり、光を透過すると夕日のような赤色に変化します。この特徴から「カルチェドーニオ」と呼ばれ、王侯貴族の間で高く評価されました。
表面にきらめく斑点は、17世紀にヴェネチアで発明された「アヴェンチュリン・グラス」によるもの。銅の結晶を含んだガラスが、自然界の鉱物の中で輝く砂金のようなきらめきを、効果的に表現しています。
14.花器

(1902~1903年頃│ボヘミア│レッツ工房)
葉が巻きつく、優美なデザインが印象的な花器。20世紀初頭のアールヌーヴォー様式の作品です。アールヌーヴォーは、植物モチーフと曲線的なデザインを特徴とし、1890年頃からヨーロッパ各地に広がりました。
表面には、金属のような艶やかな光沢が見られます。これは、鉛や錫などを溶かした液体をガラスに焼き付ける「ラスター彩」技法で表現されています。銀化した古代ガラスの出土品への憧れが、19世紀後半から始まる欧米でのラスター彩ガラスの流行を生み出しました。特にレッツ工房のラスター彩ガラスは、有機的かつ抽象的なデザインが魅力的であり、工房と芸術家やデザイナーとの協働により、200を超えるバリエーションが生み出されました。
14.花器

(1902~1903年頃│ボヘミア│レッツ工房)
葉が巻きつく、優美なデザインが印象的な花器。20世紀初頭のアールヌーヴォー様式の作品です。アールヌーヴォーは、植物モチーフと曲線的なデザインを特徴とし、1890年頃からヨーロッパ各地に広がりました。
表面には、金属のような艶やかな光沢が見られます。これは、鉛や錫などを溶かした液体をガラスに焼き付ける「ラスター彩」技法で表現されています。銀化した古代ガラスの出土品への憧れが、19世紀後半から始まる欧米でのラスター彩ガラスの流行を生み出しました。特にレッツ工房のラスター彩ガラスは、有機的かつ抽象的なデザインが魅力的であり、工房と芸術家やデザイナーとの協働により、200を超えるバリエーションが生み出されました。
ナレーター:儒烏風亭らでん

儒烏風亭らでん
hololive DEV_IS所属で「ReGLOSS」のメンバー。学芸員資格を持ち、美術・工芸・写真・絵画などのお話も配信されています。
ナレーター:儒烏風亭らでん

儒烏風亭らでん
hololive DEV_IS所属で「ReGLOSS」のメンバー。学芸員資格を持ち、美術・工芸・写真・絵画などのお話も配信されています。
ミルフィオリ・パテラ形杯
10月15日から展示予定

(紀元前1世紀~紀元後1世紀│東地中海沿岸域)
花文様と二重の円文様のガラス片で制作されたモザイク・グラスの杯。使用されているガラス片は、断面が花や円文様になるように色ガラスを組み合わせ、引き延ばしたガラス棒を裁断して作られます。こうして生み出された金太郎飴のように同じ柄のガラス片は、トンボ玉に用いられたり、型に敷き詰めて器に成形したりしました。
モザイク・グラスの発祥は、紀元前15世紀頃のメソポタミアに遡ります。手間のかかる技法ゆえ、古代ローマ帝国では高級ガラスとして珍重されました。作品名にある「パテラ」とは膝のお皿の骨の事で、杯の形状が似ていることから、パテラ形と呼ばれています。また、花文様のモザイク・グラスは、イタリア語で千の花を意味する「ミルフィオリ」とも呼ばれています。
ミルフィオリ・パテラ形杯
10月15日から展示予定

(紀元前1世紀~紀元後1世紀│東地中海沿岸域)
花文様と二重の円文様のガラス片で制作されたモザイク・グラスの杯。使用されているガラス片は、断面が花や円文様になるように色ガラスを組み合わせ、引き延ばしたガラス棒を裁断して作られます。こうして生み出された金太郎飴のように同じ柄のガラス片は、トンボ玉に用いられたり、型に敷き詰めて器に成形したりしました。
モザイク・グラスの発祥は、紀元前15世紀頃のメソポタミアに遡ります。手間のかかる技法ゆえ、古代ローマ帝国では高級ガラスとして珍重されました。作品名にある「パテラ」とは膝のお皿の骨の事で、杯の形状が似ていることから、パテラ形と呼ばれています。また、花文様のモザイク・グラスは、イタリア語で千の花を意味する「ミルフィオリ」とも呼ばれています。
